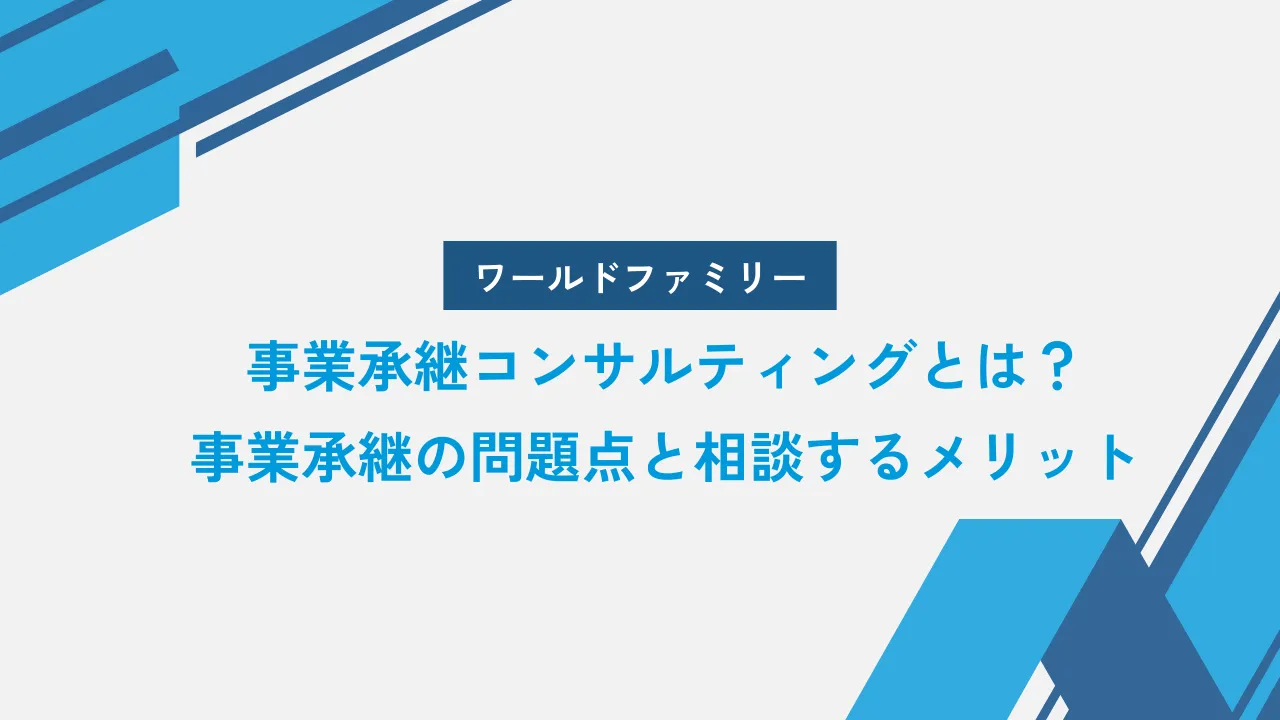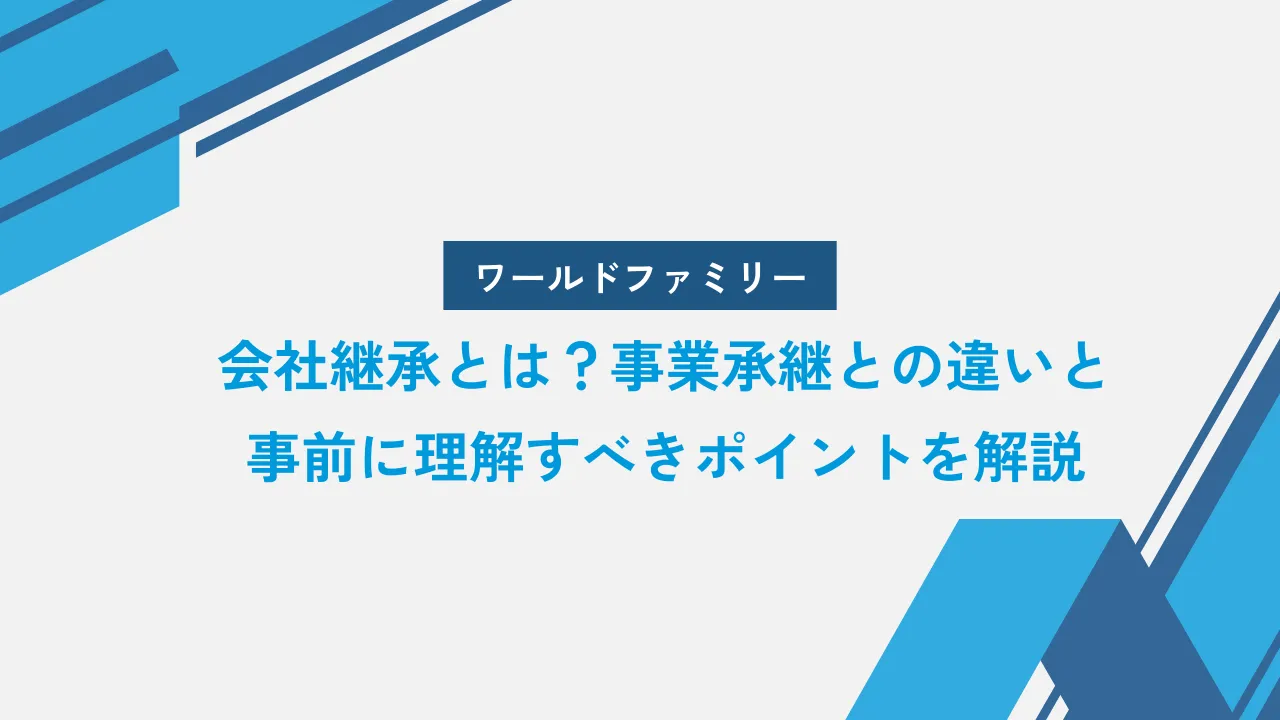事業承継の適切な進め方を解説!利用できる税制優遇や補助金なども紹介
2024.06.14 事業承継・相続
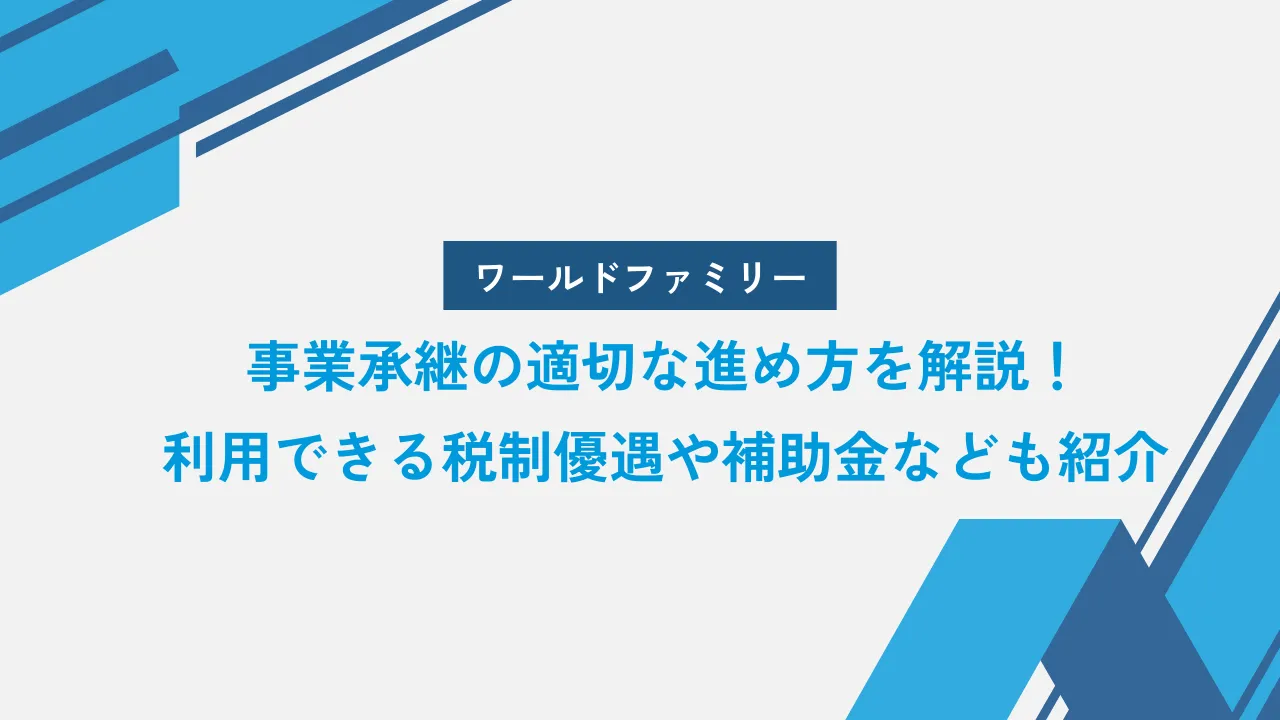
目次
事業承継を検討していても、そもそもどのように進めればよいのか迷われる方は多いでしょう。適切な進め方を知らないと、予期せぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
本記事では、事業承継の進め方を詳しく解説します。進める過程で利用できる税制優遇や補助金など、負担を軽減するポイントもわかるようになっているので、ぜひ参考にしてください。
事業承継の進め方
事業承継をスムーズに進める手順は、以下のとおりです。
- 承継方法の選択
- 経営状況や課題などの把握と改善
- 事業承継計画を立てる
- 事業承継の実行
ひとつずつ解説します。
1.承継方法の選択
まずは承継方法を検討して決定しなければなりません。事業承継は承継先によって、以下の3種類に分けられます。
- 親族内承継
⇒経営者の親族へ承継する - 親族外承継
⇒役員や従業員へ承継する - M&A
⇒社外の第三者へ承継する
なお、承継先は選定の簡易さと費用を抑えられる点から、親族内承継→親族外承継→M&Aの順で検討するのが一般的とされています。
2.経営状況や課題などの把握と改善
承継方法が決まったら、承継までにすべきことを把握するために、経営状況や課題などを洗い出しましょう。とくに経営課題が残ったまま事業承継してしまうと、後継者に負担をかけることになります。
すべての課題をクリアするのは難しくとも、承継の時点で明確になっているだけでも後継者にとっては負担なく取り組めるでしょう。
また、M&Aで事業承継する場合も、経営者が的確に経営状況を把握していないと、買い手を見つけるのが難しくなるかもしれません。承継のための準備や周知などと並行しながら、課題改善にも取り組みましょう。
3.事業承継計画を立てる
親族内承継もしくは親族外承継を行う場合は、事業承継計画を立て、承継の対象となるものの整理や方針、スケジュールなどを決めます。また、株式などの資産や権限などの移譲の範囲なども明確に決めておくと、後々のトラブルを未然に防げます。
M&Aで承継する場合は専門のM&A仲介機関を選定して条件などを決め、買い手とのマッチングを進めましょう。よりよい条件で譲渡するためにも、計画を立てて経営改善を図ることが重要です。
なお、承継時に税金や専門家への依頼料などの費用がかかる場合もあるので、資金繰りの計画を立てることも忘れてはいけません。将来の事業承継を見越して、早い段階から準備を進めましょう。
4.事業承継の実行
あらかじめ立てた計画に沿って、事業承継を実行します。後述する税制優遇や補助金などの制度は最大限活用すれば、承継時の経済的負担を軽減できます。
また、承継後も会社が円滑に経営できるように、可能な限りアフターサポートにも努めましょう。自然な形でサポートするのであれば、会長や顧問という肩書きで会社と関わったり、後継者への引き継ぎ期間を設けたりする方法があります。
事業承継時に利用できる税制優遇や補助金などの制度4つ
事業承継では多額のコストが発生するので、少しでも負担を抑えるために税制優遇や補助金を活用しましょう。事業承継時に利用できる、主な税制優遇や補助金制度を4つ紹介します。
- 事業承継税制
- 事業承継・引継ぎ補助金
- 各自治体の補助金
- 低利融資
税金や資金の対策ができるので、それぞれ押さえておきましょう。
1.事業承継税制
事業承継税制とは、事業承継にともなう相続税・贈与税の納税猶予を受けられる制度です。制度利用後に相続人が死亡すると、その税金が免除されます。
さらに、2018年からは一定の要件のもと、2027年までに限り一層有利に承継できるようになりました。例えば、納税猶予の対象となる非上場株式などの制限が撤廃されたり、納税猶予割合が100%にまで引き上げられたりなどです。
事業承継税制の申込みや問い合わせは、都道府県の担当窓口で受付をしています。承継時の税負担を大きく軽減できる制度なので、積極的に有効活用しましょう。
2.事業承継・引継ぎ補助金
事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継をきっかけに新しい取り組みを行う中小企業や小規模事業者に対して、取り組みに関わる経費の一部を補助する制度です。支援の対象は、以下の3つとなっています。
| 申請類型 | 補助対象 | 補助率※1 | 補助上限 |
| 経営革新枠 | 経営資源引継ぎ型創業や事業承継(親族内承継実施予定者を含む)、M&Aを過去数年以内に行った者、または補助事業期間中に行う予定の者 | 1/2・2/3 | ~600万円 |
| 1/2 | 600万~800万円※2 | ||
| 専門家活用枠 | 補助事業期間に経営資源を譲り渡す、または譲り受ける者 | 1/2・2/3 | ~600万円※M&A未成約の場合は~300 万円 |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 事業承継やM&Aの検討・実施等に伴って廃業などを行う者 | 1/2・2/3 | ~150万円 |
※1補助率は、補助対象の要件により異なる。
※2一定の賃上げを実施する場合、補助上限を600万円から800万円に引き上げ。
参考: 中小企業庁
経営革新枠と廃業・再チャレンジ枠は承継後の事業を有利に進める内容ですが、専門家活用枠はM&Aでこれから事業をする予定の方が使える内容です。M&Aでの事業承継を検討している場合は、ぜひ有効に活用してください。
事業承継・引継ぎ補助金を利用したい場合は、公式サイトから申請内容などの詳細を確認できます。
【参考】
3.各自治体の補助金
各自治体でも、事業承継の際に使える補助金が用意されている場合があります。例えば、岡山市では市内の事業者が事業承継する際、コンサルティングや事業承継計画の作成などにかかる経費を補助してくれます。
【参考】
拠点を構えている自治体に事業承継に関連する補助金がないか、あらかじめ確認しておきましょう。
4.低利融資
事業承継時に自社株式や事業資産を買い取る場合や相続税・贈与税の支払いをする場合に、日本政策金融公庫から最大7億2000万円(うち運転資金4億8000万円)の融資を受けられます。さらに、通常金利よりも低い特別金利が適用されるので、返済時の負担が小さくなります。
事業承継をする時期までに必要資金の確保が難しいようであれば、低利融資の利用を検討してみてください。
【参考】
事業承継の進め方を知ってスムーズに会社を引き継ごう
事業承継を進める際は、時間の余裕を持って入念に計画を立てたうえで進めることが重要です。実際に、事業承継を進める過程でさまざまな過大に直面するため、進め方を把握しておかないと時間がかかってしまうでしょう。
また、公的な税制優遇や補助金などを駆使すれば、経済的負担を最小限にしながら承継できます。事業承継の資金を工面するのであれば、法人保険を利用するのもひとつの方法です。どのような保険が最適なのかわからない方は、法人保険の専門家に相談してみることをおすすめします。
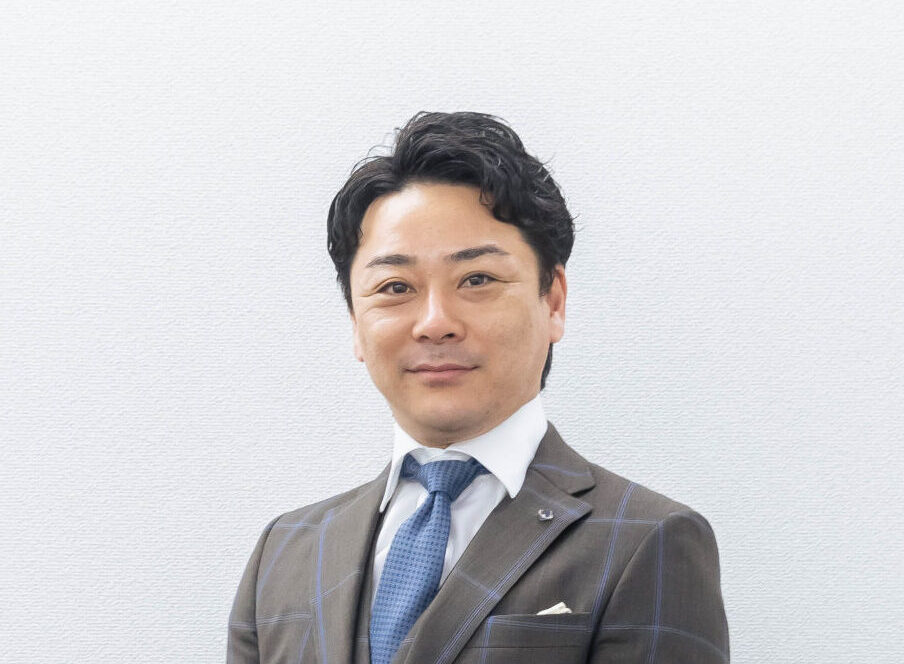
片岡 伸哉Shinya Kataoka
MDRT会員